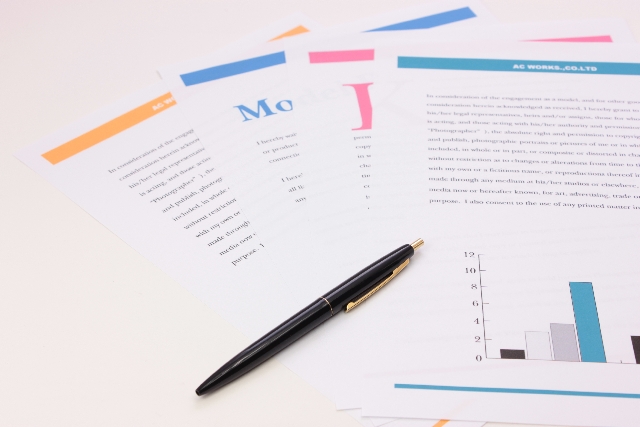


仕事を辞めるとき、恋人や同居の家族には、どの程度まで相談すべきでしょうか??
大変個人的なコトをお聞きしてしまってスミマセン。
どうしても、一人で判断できなかったもので、アドバイスをください。
5年間勤めた会社を辞めたいと思っています。
現在、転職の当てはなく、当分はアルバイトと失業保険で過ごそうと思っております。
今までにも1度転職経験があり、その時は退職後1ヶ月弱で次の仕事(現在の職場)が決まりました。
今回は社会情勢からみても、そう簡単には行かないだろうと思っています。
仕事を辞めるとき、恋人や同居の家族には、どのように相談すべきでしょうか??
もうこのまま続けても毎日が辛いだけで自分が成長できる可能性もないため、辞める意思は固まっているのですが、
仕事を辞めることで、一時的に家族には負担を掛けてしまうコトになるでしょうし、
恋人にも失望されてしまうのではないかと思うと、怖くていままで相談出来ませんでした。
いま、相談して、許してもらうべきでしょうか?
それともそれは、相談して「いいよ」と言って貰いたいだけの甘えでしょうか?
退職届を提出してから、報告するのでは遅いでしょうか?
それとも、退職自体が間違っているのでしょうか。
仕事が嫌で仕方ないから、少し立ち止まって整理したいなんて、今更甘えた理由でしょうか。
大変個人的なコトをお聞きしてしまってスミマセン。
どうしても、一人で判断できなかったもので、アドバイスをください。
5年間勤めた会社を辞めたいと思っています。
現在、転職の当てはなく、当分はアルバイトと失業保険で過ごそうと思っております。
今までにも1度転職経験があり、その時は退職後1ヶ月弱で次の仕事(現在の職場)が決まりました。
今回は社会情勢からみても、そう簡単には行かないだろうと思っています。
仕事を辞めるとき、恋人や同居の家族には、どのように相談すべきでしょうか??
もうこのまま続けても毎日が辛いだけで自分が成長できる可能性もないため、辞める意思は固まっているのですが、
仕事を辞めることで、一時的に家族には負担を掛けてしまうコトになるでしょうし、
恋人にも失望されてしまうのではないかと思うと、怖くていままで相談出来ませんでした。
いま、相談して、許してもらうべきでしょうか?
それともそれは、相談して「いいよ」と言って貰いたいだけの甘えでしょうか?
退職届を提出してから、報告するのでは遅いでしょうか?
それとも、退職自体が間違っているのでしょうか。
仕事が嫌で仕方ないから、少し立ち止まって整理したいなんて、今更甘えた理由でしょうか。
私なら、家族や恋人に対し、事前に仕事を辞めようと思っていることを伝えます。
どのようにも何も辞めることを普通に伝えたらいかがでしょうか?
反対されるかもしれませんし、以外に良いアドバイスもらえる可能性もあります。
辞めてから伝えられたら家族や恋人はもっと失望しますよ。何のための家族なんですか?言いにくいことも言えるのが家族や恋人だと思います。率直に伝えてアドバイスや叱咤激励をしてもらいましょう。
※それよりも家族に負担をかけるのであれば、私なら辞めません。もしあなたが結婚されていて仕事辞めたら奥さんや子供が路頭に迷うんですよ。それを考えたらいくら辛くても辞められません。
また「許しもらう・・」という表現使われていますが、決めるのはあなたですよ。
考え方から改めるべきだと思います。書かれている通り、誰かに共感してもらいたいだけだと思います。ちょっと甘えてる感じがします。
一番いいのは、次の仕事見つけてから辞めることだと思いますが、それは出来ないのでしょうか?
それが一番スムーズに話が進むと思います。
どのようにも何も辞めることを普通に伝えたらいかがでしょうか?
反対されるかもしれませんし、以外に良いアドバイスもらえる可能性もあります。
辞めてから伝えられたら家族や恋人はもっと失望しますよ。何のための家族なんですか?言いにくいことも言えるのが家族や恋人だと思います。率直に伝えてアドバイスや叱咤激励をしてもらいましょう。
※それよりも家族に負担をかけるのであれば、私なら辞めません。もしあなたが結婚されていて仕事辞めたら奥さんや子供が路頭に迷うんですよ。それを考えたらいくら辛くても辞められません。
また「許しもらう・・」という表現使われていますが、決めるのはあなたですよ。
考え方から改めるべきだと思います。書かれている通り、誰かに共感してもらいたいだけだと思います。ちょっと甘えてる感じがします。
一番いいのは、次の仕事見つけてから辞めることだと思いますが、それは出来ないのでしょうか?
それが一番スムーズに話が進むと思います。
扶養の手続きについて。全く理解できないので教えて下さい。
今年の10月末に妊娠により退職しました。翌日から旦那の健保に入れると思っていたのですが未だ入れず困っています。
被扶養者の資格について教えて下さい。
現在の私の状態は
・11月1日から無職
・妊娠6カ月の為、失業保険受給期間延長手続きをした
・前職場の保険の任意継続はしていない
税制上の扶養には年間の総所得が103万以上なので加入できない事は理解できるのですが、
健保の場合は向こう一年間の継続的収入の見込みなので、
無職(無収入)となった私は11月1日から旦那の健保に加入できるはずではないでしょうか?
失業保険受給期間延長をしたから(ゆくゆくは失業保険をもらうから)健保に入れないなんてことはありえるのでしょうか?
なぜ旦那の健保に入れないのか分からず、でもこのまま保険無しの状態が続くのは困るので、すぐにでも国保に入ったほうがいいのか本当に困っています。
無知でお恥ずかしいですが、詳しい方どうか教えて下さい。
今年の10月末に妊娠により退職しました。翌日から旦那の健保に入れると思っていたのですが未だ入れず困っています。
被扶養者の資格について教えて下さい。
現在の私の状態は
・11月1日から無職
・妊娠6カ月の為、失業保険受給期間延長手続きをした
・前職場の保険の任意継続はしていない
税制上の扶養には年間の総所得が103万以上なので加入できない事は理解できるのですが、
健保の場合は向こう一年間の継続的収入の見込みなので、
無職(無収入)となった私は11月1日から旦那の健保に加入できるはずではないでしょうか?
失業保険受給期間延長をしたから(ゆくゆくは失業保険をもらうから)健保に入れないなんてことはありえるのでしょうか?
なぜ旦那の健保に入れないのか分からず、でもこのまま保険無しの状態が続くのは困るので、すぐにでも国保に入ったほうがいいのか本当に困っています。
無知でお恥ずかしいですが、詳しい方どうか教えて下さい。
通常であれば、認定される状態です。
健保組合によって、詳細な認定基準が異なるので、加入できない理由を会社経由で確認してもらったほうがいいでしょう。
もし、会社が聞いてくれないようなら、健保組合に直接電話してみてください。
夫の保険証に、健保組合の名称と電話番号の記載があります。
考えられるのは、失業保険の受給待機期間中は加入できないという判断かもしれません。
もしかしたら、妊娠中という情報が伝わっていないことも考えられます。
健保組合によって、詳細な認定基準が異なるので、加入できない理由を会社経由で確認してもらったほうがいいでしょう。
もし、会社が聞いてくれないようなら、健保組合に直接電話してみてください。
夫の保険証に、健保組合の名称と電話番号の記載があります。
考えられるのは、失業保険の受給待機期間中は加入できないという判断かもしれません。
もしかしたら、妊娠中という情報が伝わっていないことも考えられます。
育児休業、失業保険について...
勤続10年以上(正社員)、結婚して3年、そろそろ子供をと思っております。
今まで、ずっと働いてきた為、収入がなくなることが不安でついつい後回しになっ
ていました。
体力的なことも考え、そろそろ真剣に子作りしたいと思います。
そこで、最近少し調べていたら給付金制度を知りました。
裕福ではないため、給付金制度を利用したいです。
ですが、制度がさっぱり理解できません。出産前産後休暇や育児休暇...
妊娠し、臨月まで出勤しないと制度を利用できないのでしょうか??
また、職場の就業規則に育児休業制度ありとなっているのですが、育児休業制度を会社に申請し、認められなかった場合、やむを得ず退職となってしまうと思うのですが、妊娠による退職は自己都合になってしまうのでしょうか?
産後、働く意志があり復帰したいと思っていても会社都合ではなく自己都合になってしまうのでしょうか??
失業保険制度を妊娠中は受けられないと思うのですが、退職後、出産、子供がある程度成長し、再び職に就こうと思った時に利用出来たりするのでしょうか??
退職日から何日以内だったら失業保険が利用できたりするのでしょうか??
アドバイス宜しくお願いしなす。
自分でも少しづつ勉強していきたいと思ってます。
勤続10年以上(正社員)、結婚して3年、そろそろ子供をと思っております。
今まで、ずっと働いてきた為、収入がなくなることが不安でついつい後回しになっ
ていました。
体力的なことも考え、そろそろ真剣に子作りしたいと思います。
そこで、最近少し調べていたら給付金制度を知りました。
裕福ではないため、給付金制度を利用したいです。
ですが、制度がさっぱり理解できません。出産前産後休暇や育児休暇...
妊娠し、臨月まで出勤しないと制度を利用できないのでしょうか??
また、職場の就業規則に育児休業制度ありとなっているのですが、育児休業制度を会社に申請し、認められなかった場合、やむを得ず退職となってしまうと思うのですが、妊娠による退職は自己都合になってしまうのでしょうか?
産後、働く意志があり復帰したいと思っていても会社都合ではなく自己都合になってしまうのでしょうか??
失業保険制度を妊娠中は受けられないと思うのですが、退職後、出産、子供がある程度成長し、再び職に就こうと思った時に利用出来たりするのでしょうか??
退職日から何日以内だったら失業保険が利用できたりするのでしょうか??
アドバイス宜しくお願いしなす。
自分でも少しづつ勉強していきたいと思ってます。
★出産手当て金
産前6週間~産後8週間の間、無給の為に給付されます。
産前6週間(42日)よりも前に退職してしまうと貰えません。
ただし、退職する場合でも、産前6週間(42日)よりも後(出産予定日に近い)に退職した場合で
さらに産休として1日でもお休みしていれば給付の対象になります。
★育児休業給付金
産前産後休暇(産休)後~お子さんが1歳になるまでの期間(育児休業中)の給付金です。
育児休業中に、2か月に1度申請をすることで、お子さんが1歳になる前日まで(延長した場合は1歳半まで)
2か月に1度、2か月分を給付できます。
育児休業中に退職となった場合は、退職した日までは給付されますが退職後は貰えません。
★失業手当て
失業保険は、退職後1ヶ月を過ぎた後の30日以内(つまりは退職日から2か月以内)に、
失業保険の受給資格延長の手続きを行っておくと
最長3年(本来の受給期間の1年を含めると合計4年まで)は、受給資格を延長することができるので
産後に再び就職活動をする時に利用出来るようになります。
産前6週間~産後8週間の間、無給の為に給付されます。
産前6週間(42日)よりも前に退職してしまうと貰えません。
ただし、退職する場合でも、産前6週間(42日)よりも後(出産予定日に近い)に退職した場合で
さらに産休として1日でもお休みしていれば給付の対象になります。
★育児休業給付金
産前産後休暇(産休)後~お子さんが1歳になるまでの期間(育児休業中)の給付金です。
育児休業中に、2か月に1度申請をすることで、お子さんが1歳になる前日まで(延長した場合は1歳半まで)
2か月に1度、2か月分を給付できます。
育児休業中に退職となった場合は、退職した日までは給付されますが退職後は貰えません。
★失業手当て
失業保険は、退職後1ヶ月を過ぎた後の30日以内(つまりは退職日から2か月以内)に、
失業保険の受給資格延長の手続きを行っておくと
最長3年(本来の受給期間の1年を含めると合計4年まで)は、受給資格を延長することができるので
産後に再び就職活動をする時に利用出来るようになります。
雇用保険の失業手当について。
仕事をやめてすぐ妊娠する前提なら、雇用保険は最初から妊娠してる手続きにしなきゃならないですか?
失業保険の手続きをしてから、妊娠したのでは、働けないから給付されないのでしょうか?
教えて下さい。
仕事をやめてすぐ妊娠する前提なら、雇用保険は最初から妊娠してる手続きにしなきゃならないですか?
失業保険の手続きをしてから、妊娠したのでは、働けないから給付されないのでしょうか?
教えて下さい。
失業保険を貰う時は、会社を退職したらすぐ申請するのがいいと思います。実際の支給は何か月か遅れて始まります。(退職理由や職場での状況ににより異なりますが)
国民年金の未納分、免除分の支払いについて
30代女性です。恥ずかしながら、国民年金の未納分があり、その支払について教えていただけたらと思います。約2年分の23ヶ月の未納分があります。内訳は、9か月分は期限切れ、5か月分はもうすぐ期限が迫っている、9ヶ月分は免除申請です。
ざっと経緯を説明すると、転職をした際にブラックな企業だったのか厚生年金に入れてもらえず国民年金扱いだったのですが、住民票を実家のままで別に暮らしていたため納付書が手元になく、両親に「後で払うので立て替えて欲しい」と頼んだのですが「会社員なのにそんなわけがない」と親が判断し(まあ当たり前ですよね)結局未納。そのまま結局は退職し、無職に。しかし不況の中、就職先はなかなか見つからず、失業保険を貰いながら就職活動をすることに。その際に免除申請もしました。現在は就職し厚生年金です。なので、ブラック企業→退職→無職→就職までの23ヶ月が未納になっています。
ここでですが・・・。期限が切れいている9か月分に関しては今どうこう出来る問題ではないので仕方がないのですが、残りの14ヶ月の部分の支払いについてです。今支払っても60歳を過ぎて任意加入して支払っても同じでしょうか?最低支払の300ヶ月まであと10年なので、ここはクリア出来そうです。なので、満額にするかどうかの話なのですが・・・。
現在は結婚をしており、夫が仕事を辞めない限り私が仕事を辞めても扶養になれます。今回は、夫が60歳の定年まで働くこと前提でお願いいたします。夫のほうが6歳年下です。また離婚しない前提でお願いします(笑)
未納になっている分と免除分を今から支払っていくのと、60歳から任意加入をして支払っていくのとでは違いますでしょうか?支給金額に影響は出ますか?無職の間、市民税の支払もままならず、最近やっと滞納分を収めたので、年金の対処が後回しになっていました(優先順位的に市民税のが先と判断しました)。
今払えるなら払った方がいいのは確かですが、どう支払っていくのがベストなのかを踏まえ、夫と相談したいと思っています。うちは家計の管理は夫なのと、家計を共にしているので必要な出費は理解してもらう必要があるので、いろいろアドバイスをいただけたらと思います。よろしくお願いいたします。
30代女性です。恥ずかしながら、国民年金の未納分があり、その支払について教えていただけたらと思います。約2年分の23ヶ月の未納分があります。内訳は、9か月分は期限切れ、5か月分はもうすぐ期限が迫っている、9ヶ月分は免除申請です。
ざっと経緯を説明すると、転職をした際にブラックな企業だったのか厚生年金に入れてもらえず国民年金扱いだったのですが、住民票を実家のままで別に暮らしていたため納付書が手元になく、両親に「後で払うので立て替えて欲しい」と頼んだのですが「会社員なのにそんなわけがない」と親が判断し(まあ当たり前ですよね)結局未納。そのまま結局は退職し、無職に。しかし不況の中、就職先はなかなか見つからず、失業保険を貰いながら就職活動をすることに。その際に免除申請もしました。現在は就職し厚生年金です。なので、ブラック企業→退職→無職→就職までの23ヶ月が未納になっています。
ここでですが・・・。期限が切れいている9か月分に関しては今どうこう出来る問題ではないので仕方がないのですが、残りの14ヶ月の部分の支払いについてです。今支払っても60歳を過ぎて任意加入して支払っても同じでしょうか?最低支払の300ヶ月まであと10年なので、ここはクリア出来そうです。なので、満額にするかどうかの話なのですが・・・。
現在は結婚をしており、夫が仕事を辞めない限り私が仕事を辞めても扶養になれます。今回は、夫が60歳の定年まで働くこと前提でお願いいたします。夫のほうが6歳年下です。また離婚しない前提でお願いします(笑)
未納になっている分と免除分を今から支払っていくのと、60歳から任意加入をして支払っていくのとでは違いますでしょうか?支給金額に影響は出ますか?無職の間、市民税の支払もままならず、最近やっと滞納分を収めたので、年金の対処が後回しになっていました(優先順位的に市民税のが先と判断しました)。
今払えるなら払った方がいいのは確かですが、どう支払っていくのがベストなのかを踏まえ、夫と相談したいと思っています。うちは家計の管理は夫なのと、家計を共にしているので必要な出費は理解してもらう必要があるので、いろいろアドバイスをいただけたらと思います。よろしくお願いいたします。
「滞納」と「免除」とは扱いが全く違うのでご注意を。
免除を承認された期間は、年金の受給資格の判定では「保険料納付済み」とされます(額の計算にも、時期により1/3又は1/2と計算される)。
・滞納分については、世帯主・配偶者にも連帯納付義務があり、差押えもあります。差押えは国税庁の担当です。いまの政治情勢では、年々取り立てが厳しくなる傾向です。
・障害年金・遺族年金が受けられない危険があります。
20歳0ヶ月から初診日又は死亡日の前々月のうち、2/3以上が納付済み(全額免除含む)でなければなりません。納付済みかどうかは、初診日の前日・死亡日の時点が基準です(初診日以降に納付した分はカウントされない)。
免除を承認された期間は、年金の受給資格の判定では「保険料納付済み」とされます(額の計算にも、時期により1/3又は1/2と計算される)。
・滞納分については、世帯主・配偶者にも連帯納付義務があり、差押えもあります。差押えは国税庁の担当です。いまの政治情勢では、年々取り立てが厳しくなる傾向です。
・障害年金・遺族年金が受けられない危険があります。
20歳0ヶ月から初診日又は死亡日の前々月のうち、2/3以上が納付済み(全額免除含む)でなければなりません。納付済みかどうかは、初診日の前日・死亡日の時点が基準です(初診日以降に納付した分はカウントされない)。
関連する情報